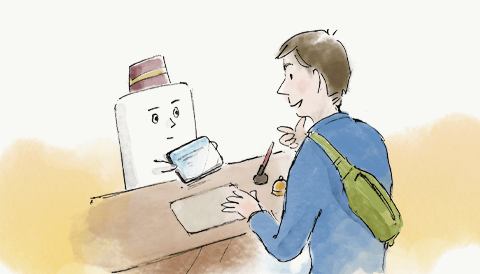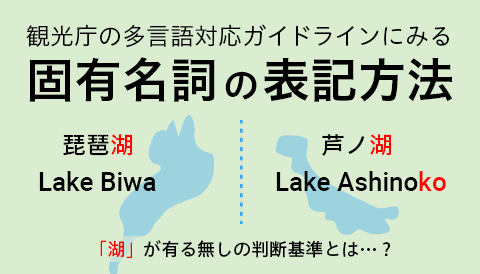ご存じですか?“地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル”
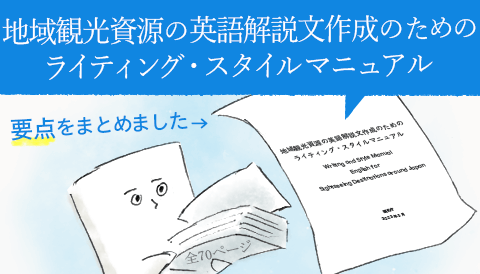
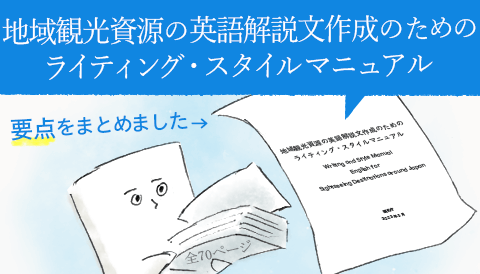
新型コロナウィルスの水際対策が昨秋大きく緩和され、また4月末には入国制限が撤廃されたことをうけて、インバウンド需要が本格的に回復しつつあります。
そのような中で、訪日外国人旅行者に日本の文化・自然・観光スポットの魅力を伝え、「また訪れたい」と感じていただくためには、各観光地の解説が理解しやすく書かれていることが鍵になります。
しかしながら現時点においては、難しすぎて理解できなかったり、知りたいことが書かれていなかったり、また、「英語の表現がおかしくて読む気にならない」など、各所の魅力を十分に伝えることができていない状況があります。
皆さまは、“地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル”をご存知でしょうか?
こちらは、観光庁が地域観光資源の多言語解説整備支援事業の一環として作成した、ネイティブ目線での魅力的な多言語解説文を作成するためのマニュアルです。
では、このライティングスタイルマニュアルには、いったいどのような内容が記載されているのでしょうか?
今回は、その一部を抜粋しながら英語解説文作成においての要点をまとめていきますので、ぜひ参考にしてください。
参照した資料:地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル(2.88MB)
英語解説文作成の重要ポイント
訪日外国人旅行者に向けた解説では、文法や表現が適正であるとともに、理解しやすく、読み手の学びや感動を深めるものであることが重要です。
以下の点が特に重要なポイントになりますので、前提として認識しておきましょう。
1. 知識や認識のギャップを理解し、補強する文章を付け加える
訪日外国人旅行者は、日本に関する知識や認識が十分ではありません。
日本文化等についてどのような知識や認識のギャップが存在するかをまずは理解しましょう。
日本人向けの日本語の解説文をそのまま英語に翻訳(すなわち直訳)するだけでは、意味が伝わらない可能性があります。そのため、日本の歴史と文化への理解を補強する情報を加えるよう工夫をします。
例:「かの信長公」
× (人名にtheはつけない)
The Nobunaga
△(外国の方には名前だけでは通じない場合がある)
Oda Nobunaga
○(原文にはない補足説明が必要)
Oda Nobunaga, one of the most powerful daimyo (feudal lords) in the sixteenth century,
2. 訪日外国人旅行者の興味・関心の把握
「面白いと思えない、価値がわからない」では、せっかく制作した解説が台無しです。
まずは、訪日外国人旅行者の視点から、それぞれの観光資源の特徴・特質の何が彼らの興味・関心を掻き立てるのかを知ります。
例えば、それらを知る方法として、SNSや口コミサイトのユーザーコメント、または地域在住の外国人へのヒアリングなども参考になります。
3. 媒体特性の考慮
解説文を掲載する媒体は、解説看板、映像、音声ガイド、パンフレット、またウェブサイトなどがあります。各媒体の用途およびその長所と短所を理解し、媒体に応じた書き方をする必要があります。
また、どの媒体においても優先度の高い情報が精選され、さっと読み取れるシンプルな文構造になっているかを意識することも重要です。
4. クオリティーの高い解説文を制作するための専門人材の確保
ネイティブ目線で推奨された特定のスタイルに則って執筆、編集、翻訳を行えるだけの専門性と経験を備えた人材の確保がきわめて重要です。日本語の情報を元にして英語解説文が作成されるケースが多いため、ライターは、日本語テキストの読解や翻訳等の経験が豊富で、日本での生活や仕事を通じて日本の文化や社会を深く理解している必要があります。
ライティング・スタイルマニュアルが推奨する “スタイルガイドライン”
ライティング・スタイルマニュアルの中には、英語解説文作成の際に基準となる”スタイルガイドライン”が記載されています。スタイルガイドラインを参考に英文作成を進めていくことで、外国人旅行者にとって違和感のない、わかりやすい解説文の制作が可能になります。
それでは、スタイルガイドラインに記載されている一部を抜粋し下記に紹介します。
日本語のローマ字表記は最小限にとどめる
英語による解説文なので、日本語(ローマ字表記)が多いと訪日外国人旅行者の理解が進みづらくなる可能性があります。読み手の日本文化・歴史・建築物についての理解を促す意義があると判断される場合に限って、日本語を取り入れることを考慮しましょう。
例:浄瑠璃⇒puppet theater (joruri)
(不自然でない限り英語の訳語を優先し、必要に応じて日本語のローマ字表記を括弧入りで添える。)
人名の表記にもルールがある
原則として、日本人の名前は、日本の慣習に従い苗字を先にします。
例:徳川吉宗⇒Tokugawa Yoshimune
海外で名前→苗字の順で広く知られている人物についてはそれに従います。
例:村上春樹⇒Haruki Murakami
時代や年代は西洋の時代区分表記に置き換える
解説文の多くの読み手は日本の時代区分と年号(元号)に馴染みが薄いと考えられるため、西洋の時代区分表記で置き換えます。
例:Taisho era (1912-1926)
数・金額の表記方法
世紀はすべてsixth century, fifteenth century のようにアルファベットで表記します。
また、1から9までの数字、および、文の先頭にある数はアルファベットで表記します。
例:Three temples, with a total of nine buildings, once stood on this mountain.
価格や料金の表記には、1から9までの数でもアラビア数字を使用します。また、yen, dollar, pound, euroなどスペルアウトせず通貨記号(¥, $, £, €)を使用します。
例:The entire estate was worth ¥8 million.
The standard fee for geisha service is ¥25,000 per hour.
時刻・時間の表記方法
- 基本的に時間の⾧さの表記では “hours”と“minutes”を使い、“hrs.”や “min./mins.”のような短縮形は使用しません。
- 午前/午後の表記には、“a.m.”/“p.m.”(ピリオドを打つこと)を使用します。13:00 とか21:00 のような表記法は使用せず、1:00 p.m.や 9:00 p.m.のように表します。
デザインに関する英語表記のポイント
英文を案内板やウェブサイトで表示する際に、制作担当者が忘れてはならない「英文表記のルール」があります。
その押えておくべきルールについて見てみましょう。
- 英文には和文フォントを用いない
英文テキストは、すべて1バイトの単位で作成されているため、1バイトの英文を和文フォント(2バイト)で表示すると、見栄えが悪くなるばかりか、「文字化け」したり、文として意味をなさなくなったりすることもあります。
- 適切なフォントを選択する
欧文フォントには、セリフ(ひげ付き)フォントとサンセリフ(ひげなし)フォントの2種類が存在します。媒体やデザインによって使い分けることになりますが、例えば案内板の場合は読みやすいセリフ・フォントがよいでしょう。
- 文字揃えを「両揃え」にしない
英文テキストでは、行は「左揃え」にするのが一般的です。両揃えでは、単語と単語の間がひらき、読みにくく、見た目も悪くなるので避けましょう。
- 適切な段落表示
案内板や印刷物では、小見出し後の最初の行の文頭はインデント(字下げ)なし、その後の段落は冒頭にすべてインデントを設けることが一般的です。ウェブサイト、QR コード・テキスト等、ネット上の文章については、段落が変わるところで行を空けます。アキを1行以上設け、段落の区別が一目瞭然となるようにします。
まとめ
今回は、「地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル」についてその一部を抜粋しながら、英文作成や翻訳においての要点をお伝えしました。世界中から日本を訪れる旅行者にとってわかりやすく魅力的な解説文の整備に、今回ご紹介させて頂きましたライティング・マニュアルをご活用いただければ幸いです。
idaでは経験豊富で日本在住歴の長いプロの翻訳者による「ネイティブに伝わる」翻訳サービスと、ウェブサイトから印刷物まで幅広い媒体に対応できる制作体制で、インバウンド施策をサポートしております。ライティング・マニュアルに沿った高品質な翻訳から各種媒体の制作も承っておりますので、お困りのことがございましたらぜひご相談ください。
最新の記事
-
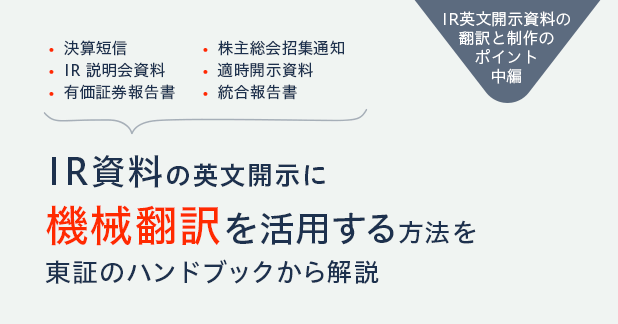
IR資料の翻訳は翻訳会社に依頼する? 機械翻訳を活用する? 東証のハンドブックから英文開示のポイントを解説
-
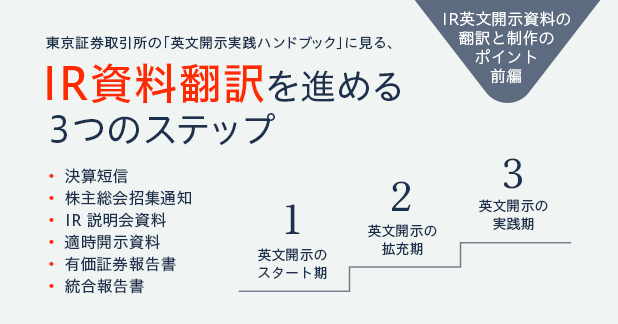
東証の「英文開示ハンドブック」に見る、IR資料翻訳を進める3つのステップ
-
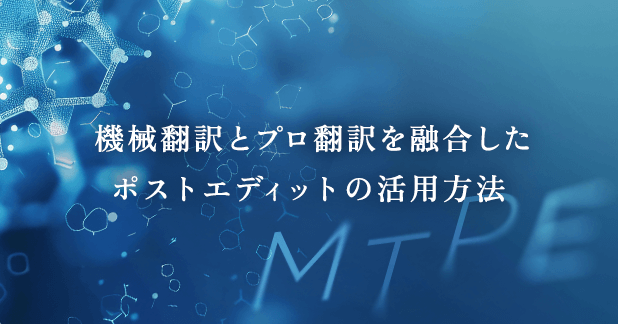
機械翻訳とプロ翻訳を融合した翻訳手法「ポストエディット」の活用方法を解説
-
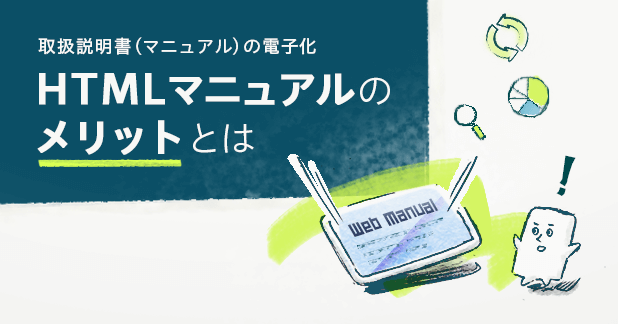
HTMLマニュアルのメリットとは
-
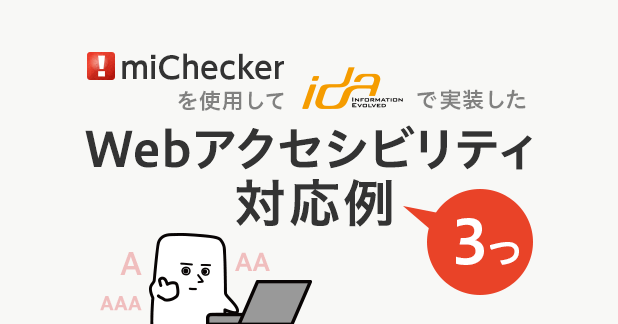
idaで実装したウェブアクセシビリティ対応例3つ
よく読まれている記事

【実践ガイド】海外向け多言語サイトの作り方と制作費用を7つのトピックで解説
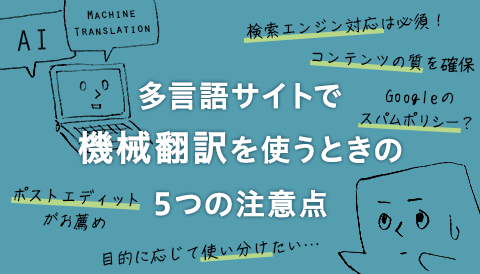
多言語サイトで機械翻訳を使うときの5つの注意点
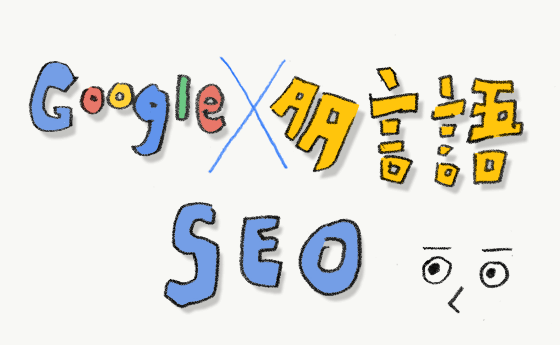
Google公式情報に見る海外向けサイトのSEO、多言語サイトのSEOポイント
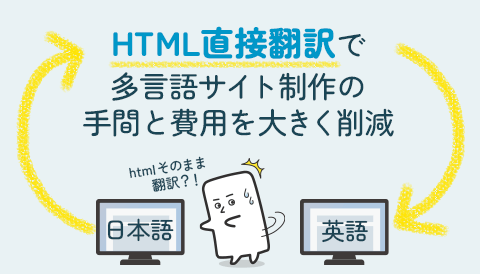
HTML直接翻訳で多言語サイト制作の手間と費用を大きく削減
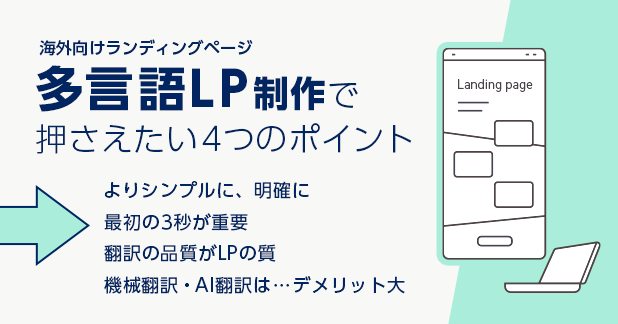
多言語LP(ランディングページ)制作で押さえたい4つのポイント